
はちがつのゆき。
≫イントロダクション
1. (勢いで書いたので修正必須)
(八月二十日、日曜日。午後ニ時半)
(SE:蝉の声)
炎天直下。夏の太陽が地面を焦がす八月の昼。
熱光線から逃げるようにして座っている拝殿の石段には、影の境界がくっきりと映っている。
額から生まれた汗は頬を通過し、重力のままに落下。石段に小さな点を描いた。
屋根越しの空は高く、遠く。原色の青と積乱雲の白はどこまでも広がっていた。
蝉の声がやかましく響く境内。独特のじっとりとした暑さが辺りを包んでいる。
「暑い・・・」
「暑いねー」
隣に座っている神明みのりは、グラスに入れた麦茶を心から幸せそうに飲みながら適当に答えた。
こんな夏場でも長袖の袴を羽織った姿は、もはや見ているだけで暑苦しい。
彼女曰く、今着ているのは夏用の袴なんだそうだが・・・。正直な所、区別は付けられそうになかった。
「はい、溝口さん」
渡されるままにグラスを受け取る。麦茶に冷やされたグラスの触感は堪らなく手に心地よかった。
一気飲みしたい衝動を抑えつつ、少しずつ麦茶を飲んでいく。
「夏だね〜」
みのりは広がる青空を見上げながら、何処までも適当に言い放ち、そして麦茶を一口飲んだ。
つられる様に空を見上げる。八月の空は青く広く、そして暑かった。
しばらく、ゆっくりとした心地よい沈黙が流れる。蝉の声だけが境内に響く、和やかな時間がゆっくりと流れていった。
・・・・・・・・・
「・・・あ、そうそう、溝口さん。えーっと、今度の土日って空いてる?」
突然思い出したかのように、甘酸っぱい緊張感を一切感じさせない口調でみのりが問いかける。
仕事のスケジュールを記憶から引っ張り出し、『多分空く』と答えた。
「それじゃね、溝口さん。その土日なんだけどさ」
みのりは立ち上がり、満面の笑顔で言い放つ。自分にとっては見上げる形になり、みのりの背中には広がる青空が見える。
そして、ワンテンポ置いて。
「雪を見に行こうよ」
蝉の鳴き声が響いている。視界の先には夏の青空が広がっている。
額に汗が滲むほどの暑さにつつまれた境内。冷えた麦茶がどこまでも心地よかった。
『雪』という単語から遥か遠い、八月。何処までも青く遠い、夏の空の下。
『雪を見に行こう』と言い切った神明みのりは、満面の笑顔で問いかけていた。
八月二十日、日曜日。午後ニ時半。
空に、風鈴の音が響いた。
(タイトル&Surubbingロゴ)
2.みのりんの母方の実家へ。 (午前10時。(出発は午前7時))
イメージとしては東北あたりの山地を想像中。あるいは中部。
山間の超ど田舎です。キャンプ道具一式は実家からレンタル。
毎年来ているみのりんは、もはや慣れっこなのですが、溝口さんはオタオタ。
言うまでもなく溝口さんは荷物持ち。簡易テントやら寝袋やら。
実はみのりん、母方の実家に行くのに、母親に連絡していません。
未だにみのりんは溝口さんの話を親には全くしてない状態だったりします。
よって、その母方の祖母に、『黙っておいてね』とか言うシーンも。
2.
8月26日。土曜日。午前9時。
(SE:電車)
車窓の景色は、緑と空の比率がだんだんと多くなっていた。
乗ったことも無い路線を乗り継ぎ、列車と俺たちはコンクリートの街から離れていくこと二時間。
気づけば4両編成にまで少なくなっていた列車の中には、もはや数える程度の乗客しかいなかった。
窓から差し込む夏の日差しは強く明るく。しっかりとした影を床に映し出している。
少し強めの冷房と、座席越しのランダムな列車の揺れが心地よかった。
「・・・みのり」
「うん?」
腕が触れる距離で、やけに上機嫌なみのりは嬉しそうな笑顔を添えて答える。
本日はいつもの巫女服ではなく、ラフな感じのパンツルックを着こなしていた。夏なのに長袖なのは、これから涼しいところに行くからだろう。
珍しくつけている髪止めが、動くたびに揺れていた。
「かなり長く電車乗ってる気がするが・・・あとどれくらいで着く?」
こうして電車に乗ってる俺だが、実は行く先は全く知らない。理由は単純で、みのりが教えてくれないからだ。
聞かされたことは『涼しい所に行くからそれなりの格好で』とだけ。雪を見に行くのに防寒具はいらないそうで、その辺りが不思議ではある。
「ん? えーっと・・・」
立ち上がり、ドアの上部に張られた路線図を見に行くみのり。表に羅列された駅名は一つとして知らない地名が並んでいた。
指差して残りの駅を確認するみのり。指は7,8回揺れたと思う。
「そうだね、あと30分って所だよ」
「了解。・・・ふぁ・・・」
日ごろの疲れが出たのか、柔らかな眠気がゆっくりと広がっている。
乗客は駅に着く度に一人一人と減り、横長の座席には俺たち二人しかいなかった。
他の客がいないのをいいことに、軽く伸びをした後、横に寝転がる。通勤ラッシュでは出来ない贅沢だった。
「着いたら起こしてくれ・・・」
「はいはい。しょうがないなぁ・・・」
みのりは腕を組み、少々不満そうにしていたが、それ以上に睡魔は強力だった。
座席から上に空を望む。時折高速で横ぎる木々の枝葉。山と田園だらけの田舎の空に夏の雲が広がっている。
「あ。ねえねえ、溝口さん」
いきなり視界をみのりの顔が塞ぐ。上機嫌なみのりは笑顔のままに簡単に言葉を続ける。
「・・・膝枕してあげよっか?」
列車は進行方向を僅かにカーブし、日差しの差し込む窓は右側から左側へ移った。
少しだけ眠気が醒めた俺に、夏の日差しが眩しく注がれていた。
『次は千畳敷〜。千畳敷駅です・・・』
ちなみに。目的地に着いたのは、これから一時間後だったりする。
2.1
電車から降りると、そこには視界360度に聳え立つ緑の山々が広がっていた。
空気は涼しく、日差しは眩しい。ビル街の中では味わえない、爽快な空気が心地よかった。思わず体を伸ばす。
ほとんど無人駅のようなホームを出る。コンビニの一つもない閑散とした駅前に一台の車が止まっていた。
少々古びた感じの車の前には人の良さそうな老夫婦がにこやかに立ち、こちらに微笑んでいる。
「おじいちゃん、久しぶりだねー!」
風合瀬(かそせ)という特殊な苗字の、みのりの母方の祖父母は突然の俺の来訪も一切驚かなかった。
白髪の割に細身ながらもしっかりとした体つきをしたお祖父さんは、手にしていた携帯電話を慣れた手つきでポケットに入れる。
「どうも。孫がお世話になっております」
「え、あ、はい、どうも・・・」
即答できなかったのは、”お孫さんにお世話されてるから”ではないはずだと、強く思いたい。
・・・・・・・・・・・・・・・
ライトバンの後部座席からは、どこまでも穏やかな山地の農村の景色が流れていった。
『雪を見に来たはずなのに、今俺は何でみのりの祖父母と話しているのか』という疑問は、やたらと話の上手い祖父母にかき消されていく。
外を見れば、高い山越しに見事な積乱雲がゆっくりと浮かび流れている。日差しは明るく眩しくて、足に当たり続けては熱くてたまらなかった。
蝉の声。山鳥の鳴き声。川から聞こえる水しぶきの音。開けっ放しの窓からは沢山の音と風が流れ込んでいた。
「いい所だよね?」
尋ねるみのりに、俺は思わず頷きを返していた。
・・・・・・・・・・・・・・・
2.2
どさっ。どさっ。
やたら立派だった風合瀬さん家の広い庭には、青色のレジャーシートが広がっていた。
その上に、みのりの祖父母が色々と陳列していく様を、縁側に座りながら呆然と見つめている。
二人が座る横にはご丁寧にも、麦茶とスイカを用意してもらっている。『日本の夏』といった風景をそのまんまコピーしたような絵になっていた。
みのりは幸せそうにスイカをほおばっている。何となく、いつもの神社の光景を連想する。
そんな中、レジャーシート上には小型のバーナー、テントと思しき布と骨組、飯ごうと鍋、ランタンといったアイテムが揃っていく。
隣に置いてあるかなり大き目のリュックサックに、お祖母さんは手際よくそれらを収納していった。
「なぁ、みのり? 風合瀬さんは何をしてるんだ?」
みのりは、冷えたスイカにたっぷりと塩を塗りたくっていた。早くも8切れ目を完食する勢いだった。
「何って・・・。準備だよ?」
「何の?」
「雪を見に行く準備だよ」
『ご飯は炊かないと食べれないんだよ』級の”当たり前”のように簡単にいい放ったみのりは、8切れ目を食べきった。
何も分からない俺は脳裏に極寒での雪中行進を連想する。まさかあんなことを夏場にやろうというのか・・・?
「もしかして・・・。これから雪山登山をするのか? やっぱり防寒具でも持ってくれば・・・」
「ううん。少し歩くけど、そんなハードなことはしないから安心していいよ」
安心しろと言われても、目の前ではかなりしっかりとした準備が進んでいた。
「大丈夫。ちょっとしたピクニックだよ」
みのりの言葉の軽さとは無縁に、用意されたリュックサックは重く大きかった。
冷えたスイカは甘くて美味しかったが、味を楽しむにはいささか目の前の不安要素が多すぎたのかもしれない。
裏手に広がる山々では、山鳥が「ぴーひょろろ」と間の抜けた声で鳴いていた。
スイカを片手に夏の空を見上げる。広がる青の中、眩しい太陽と積雲がゆっくりと流れている。
しゃくっ、という音を立ててスイカをかじる。ここで取れたというスイカはとても甘く、かけすぎた塩がやたらしょっぱかった。
・・・・・・・・・・
2.3

『大戸瀬山脈遊歩道入り口 山頂まで4.5km』
風合瀬さんのライトバンで連れて行かれた先には、そんな立て札が待ち構えていた。
登山客用の駐車場は、山地特有の見晴らしのいい崖の上のような所にこじんまりと存在していた。
入り口と思しき道には、丸太を置いてそこに土を固めたような、段差を無理矢理に作った階段が手招きをしている。
木陰の下、風は涼しくて心地よく、蝉の声ですらどこか爽やかに感じた。
「さてっと。溝口さん、それじゃ行こうか?」
みのりは小ぶりなリュックを背負いながらに言う。その後に、風合瀬さんの用意した巨大リュックを指差した。
「・・・いや、その・・・なんだ。未だに状況が飲み込めなかったりするんだが」
未だに状況を理解し切れていない俺に、風合瀬さんは首をかしげた。
「おや?みのりちゃんは春樹君に説明してなかったのかな?」
「うん。何も言わないのも面白いかなーと思って」
「はっはっは。それは面白い。よくもまぁ、春樹君は何も聞かされずにこんな田舎まで来たものだ」
爽やかに笑う風合瀬さんとみのり。当の俺は先程から疑問符を浮かべっぱなしである。
「みのりちゃん。春樹君に説明してもいいかな?もしもの場合は春樹君みたいな男手は重要だからね」
「うーん。”雪”について以外だったらいいよ」
そんなわけで、ここまで来てやっと風合瀬さん(&みのり)から、これからのプログラムが教えられた。
みのりの言う”雪”の見える場所はここから離れた所にあり、それこそキャンプで一泊しなければ到達できないらしい。
道のりは決してハードではないので、ゆっくりと歩いても明日の昼には確実に着く距離なんだそうだ。
「それじゃ、みのりちゃんを頼んだよ。春樹君」
風合瀬さんは最後にその言葉を、俺の肩を掴んで言い聞かせるように言った。がっしりとした握力に、思わず首を縦に振る。
そのままライトバンに戻ろうとする風合瀬さんに、みのりが慌てて声をかけた。
「あ、おじいちゃん。あのね・・・。今日私がここに来たこと、お母さんとかには秘密にしておいてね。溝口さんの事、まだ知らないんだから」
風合瀬さんは年に似合わずきょとんとした表情をし、その後に大きく笑った。みのりは少しだけ頬を紅くしてそっぽを向く。
「はっはっは!分かったよみのりちゃん。 ・・・いやぁ、若いっていいなぁ春樹君。私も昔を思い出してしまったよ」
一通り笑った後、風合瀬さんはライトバンのドアを開け、古びたエンジンをかけた。そのままライトバンに乗って風合瀬さんは家に戻っていこうとし・・・。
・・・300mくらい車で走った後に突如バックで戻ってくる。5、60キロでバックする車を見たのは初めてだったかもしれない。
唖然としている二人の前に、風合瀬さんは笑顔でライトバンから再び現れた。何となくビデオの巻き戻しを連想する。
「聞き忘れていたことがあったよ。 ・・・春樹君、まぁちょっと来たまえ」
答えを言う前に、風合瀬さんの腕は完全に俺の首に固定。老人とは思えないような屈強な力で引っ張られる。無理矢理もいい所だった。
そして、みのりを置いていく形でライトバンの影にまで連れて来られる。
「はっはっは、私もまだ若いかもしれんなぁ。心が躍るよ」
風合瀬さんは豪快に笑う。首に回された腕には見かけ以上の力がしっかりと篭っていた。
「さて・・・。春樹君に少し聞きたいことがあってね・・・」
声のトーンがいきなり落ち、音量も一気に落ちた。真剣な話なのかと、俺も少し冷静になる。
「な、なんですか?」
「・・・・・・・」
沈黙が重たい。思わず、首の痛みも忘れて冷静になった。
真剣に、風合瀬さんの次の言葉を待つ。
「・・・。・・・春樹君は、みのりちゃんのどこが良かったのかな?」
吹き出した。思わずムセた。あまりに突然だった。
「ごほっ、ごほっ・・・。 ・・・えーと、その・・・」
「はっはっは、照れんでいいよ。どうだ?この爺さんに少し教えてくれないかね?」
笑顔は絶やさずに言葉自体も優しげだが、首に回っている腕には万力の様にゆっくりと力が上がっていたのが分かってしまった。明白な脅迫である。
みのりといい、この風合瀬さんといい、この一家の腕力はどうなっているのだろう。そんなことを思う。
言わなければ、このまま風合瀬さんは俺の首をへし折るつもりだろう。この老人はそんな凄味を持っていた。
「・・・・・・・・・みのりには言わないで下さいよ?」
「大丈夫。男の約束だ」
・・・・・・・・・・
数秒後。心から面白そうに馬鹿笑いする風合瀬さんと羞恥に震える俺を、不思議そうにみのりは見つめていた。
満面の笑顔で、今度こそ家に帰っていく風合瀬さん。俺的要注意人物リスト1位はエンジンを響かせて帰っていった。
開きっぱなしだったライトバンの窓から風合瀬さんの思い出し笑いの声が聞こえて、俺は若干の頭痛を感じた。
・・・・・・・・・・・
登山口前に俺とみのりだけが残される。今先程のアレコレのせいで、少しだけ動悸が早まっているのを感じた。
「よしっ、それじゃ溝口さん。レッツゴーだよ」
「あ、ああ・・・」
目の前に威圧的に鎮座している、年季の入った巨大リュックを背負う。
寝袋などのかさ張る物が入っているためか、リュックは思っていた以上には重くなく、それ以上に背負いやすかった。
恐らく収納が上手かったのだろう。重量は上手い形に背中に分散され、これなら散歩も難なくこなせそうだ。
みのりのリュックとは五倍以上も大きさに差があるのが若干不服だったが、筋力の差ということで我慢することにする。
・・・・・・・・・
一歩を踏み出す度に、辺りを彩る景色が変わっていく。
楽しそうなみのりの笑顔。夏の日差し。山鳥の声。土を踏んだ時の微かな感触。森林の匂い。涼しい風。
今日の朝まで予想だにしなかったハイキングもどきだが、これもまた楽しいのではないかと前向きに考えられた。
たまには、こんな休日もいいのかもしれない。
二人の頭上に広がる夏の青空は、綺麗な青をどこまでも広げていた。
3.山道 (午前11時〜午後1時)
歩きます。ひたすらに歩きます。山地なんで辺りは涼しかったりします。
荷物量か、あるいは若さの差か、先にへばる溝口さん。ヘタレー。
一応は遊歩道を歩いているので、歩きやすく、景色もそれなりにいい感じ。
ほんの時折、すれ違う登山客も。
山に登るという感じではなく、ひたすらに歩いていく道が続きます。
3.

7月30日、午前11時。
ざっ、ざっ、ざっ。
歩く一歩ごとに、大地と枯れ枝を踏む音が生まれる。
久しぶりの登山ということと、背中の荷物のおかげで額に汗が滲んできていた。息も鼓動も上がっていた。
それに対するように、前方を歩くみのりは終始楽しそうに、鼻歌交じりに進んでいく。
山鳥の鳴き声が遠くから途切れなく聞こえる。
爽快に晴れた青空から降り注ぐ夏の日差しは明るく強く。高原特有の涼しさが心地よかった。
澄み切った森林の空気を吸って、一歩一歩進んでいく。
「うーん!やっぱり山はいいよねー!心が洗われる気分だよね?」
みのりは軽く伸びをしながら、心底楽しそうに言う。
「・・・年寄りくさいな、みのり」
がっ。
繰り出された拳は、スナップがいい感じに効いていた。腹部が痛い。
「ごふっ・・・。仮にも女の子がグーで殴るな、グーで・・・」
「失礼なことを言う溝口さんが悪いんだよ。まったくもう、溝口さんは風流からは程遠いなぁ・・・」
「もしかしたら今日から突如、風流を感じないと死ぬような男になるかもしれないぞ」
「あー、はいはい。期待はしてないよ・・・」
大袈裟な溜息を一つ。こんな会話と平行しながら歩いていく。
待ち受けていた山道は想像していたよりも平坦で広い道が続いていた、その中を並ぶように歩いていく。
夏の明るい木漏れ日が地面に綺麗なコントラストを作り、柱の様に地面へと伸びている。
「あ。 ・・・溝口さん、あの花な〜んだ?」
「知らん」
「即答すなっ!せめて何秒かは考えようよ、溝口さん・・・」
「自慢じゃないが、俺はヒマワリとチューリップ以外の花は知らないぞ」
「本当に自慢じゃないと思うよ・・・」
クルマバナ、コバキボウシ、シモツケ、バイケイソウ、アキノキリンソウ、ハクサンフウロ。
花を指差しては名称を言うみのりだが、恐らく1時間も経たずに忘れてしまっているだろうと確信する。
「詳しいな・・・」
「小さい頃からお祖父ちゃんと登ってたからね。こういった植物を楽しむのも、登山の楽しみなんだよ」
「ふむ・・・。それじゃみのり、食える草はどれだ?」
返答は盛大な溜息だった。
・・・・・・・・・
「ほらほら。歩きが遅くなってるよ?まだまだまだまだ先は長いんだから頑張ってね、溝口さん」
笑顔は心を癒せても、くたびれた足は癒せないことを学習する。
歩き始めて一時間は経っただろうか。日ごろの運動不足もたたってか、息が相当上がってしまっていた。
未だに汗一つかかずに悠々と歩いていくみのり。表情は笑顔で、まったく疲れてないようにすら見える。
もしかしたら、みのりは裏で長距離ランナーでもやっているでは・・・とすら思えるくらいの差があった。少々悔しい。
「ちょっと休憩しようか? ・・・はい、溝口さん。麦茶だよー」
みのりのリュックから現れた麦茶のペットボトルは来る前に凍らせておいたらしく、未だに解け切れてない麦茶の氷がつららの様に浮いていた。
受け取った手に心地よい冷気を感じる。急ぐようにキャップを外し、勢いよく飲む。氷点ぎりぎりまで冷えた麦茶が喉を潤していく。
「ぷはーっ!!」
「あははっ。いい飲みっぷりだね。 ・・・って、うわっ。そんなに飲んじゃ駄目だってば!」
このまま一気に500mlを飲み干そうとする俺から、みのりは半ば力づくにペットボトルを奪い取る。
みのりも一口二口飲んで、そのまま麦茶はリュックの中へ。
「駄目だよ溝口さん。まだまだ先は長いんだからね。多少は後を考えて飲まなきゃ駄目だよ?」
「はいはい・・・」
「”はい”は一回! …っていうお説教があったね。溝口さんもよく言われたクチかな?」
何で俺は、こんな山奥でみのりに説教されているのだろうと少しだけ思う。馬鹿にするように山鳥が遠くで高く鳴いた。
「ところでみのり。あとどれくらい歩くんだ?」
「うん? えーっとね・・・」
道の先には山脈が波形のように聳え立っている。その中でみのりはその山の一つを指差した。
「あそこの頂上で、お弁当食べようね」
二人の間を一陣の弱い風が通り抜けた。お互いの髪が揺れた。
遠かった。目指す目標地点は、やたら遠くに見えた。
素敵に強烈な宣告は、満面の笑顔から放たれてしまった。
「大丈夫大丈夫。確かに遠くに見えるけど、歩いてみると結構すぐ着いちゃうからね」
溜息をつく間もなく、みのりに引っ張られるように再び山道を歩き始める。
やたらと嬉しそうなみのりの笑顔が木漏れ日に映えていた。
その日、頭上の空には原色の青と積雲の白が高く遠く広がっていた。
自宅付近では感じることの出来なかった、湿気の薄い爽快な涼しい空気を目一杯に感じる。
濃厚な緑の匂いを感じながら、生命力溢れる道を歩いていく。
しばらく歩くと、森林地帯を抜けたためか視界が一気に開けた。
眼前に広がる広大な緑の大地を見下ろす。心地よい風が髪を揺らした。
”大自然”の名が相応しい圧倒的な景色に、思わず頬が緩んだ。
隣でみのりは「来てよかったでしょ?」と問いかけ、俺は素直に首を縦に振っていた。
4.お昼ご飯 (午後1時〜午後2時)
みのりんお手製弁当です。から揚げ、たこさんウインナーは必須アイテム。
やたらとほのぼの系なラブラブっぷり。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「「到達ー!!!」」
山頂への最後の階段を踏んだ時。人はきっと叫ばずにはいられないのだ。
これこそが登山の素晴らしさなのだと、みのりは熱く強く語った。
そんなわけで、万歳のポーズを添えて叫んでみたわけだが・・・周りに人がいなくて本当に良かったと思う。少々恥ずかしい。
「いい眺めだねー!」
山頂から見える景色はどこまでも広く。地平線すら見えそうなくらいに続く山々に畏敬を感じずにはいられない。
時間も正午を過ぎ、日差しも強くなっていた。都会では恨めしく感じる日差しも、この場所においては心地よいくらいに感じる。
みのりは爽やかに、それこそ『いい汗かきました』の雰囲気全開で山頂からの景色を楽しんでいた。
「よし!みのり、昼飯だ!!」
「うわっ。途端に元気になってるよ・・・。さっきまでゼーゼー言ってたのに・・・」
みのりは呆れながらリュックを下ろし、中からレジャーシートを広げる。どこかのキャラクターがプリントされた、可愛らしいシートだった。
続いて自分も背中の重荷を下ろす。手にずっしりとした重みを感じ、我ながらよく背負ってこれたものだと感心した。
「あー、重かった・・・」
「うん。お疲れ様」
一畳程度のレジャーシートの上にちょこんと座ったみのりは、リュックから大き目の弁当箱を取り出していた。
さらにはコップや箸や取り皿も並び、準備は万端。
自分も靴を脱いでシートの上であぐらをかく。シート越しの草花が柔らかいクッションになっていて心地よかった。
「言うまでもなく、手作りのお弁当だからね」
弁当箱を両手に持ったみのりの顔には、思わず頭を撫で回したくなるような満面の笑顔が浮かんでいた。
「それじゃ、開けるよー?」
ぱかっ。
俺はこの瞬間、生涯でもっとも勢いのあるサムズアップをしたと確信している。
弁当箱の中には見事なまでの『理想のお弁当』が広がっていた。定番の鳥のから揚げ、卵焼きは勿論のこと、かの『たこさんウインナー』まで入っている。
その他、カニクリームコロッケにミニハンバーグ、マカロニサラダ等々。彩りに添えられたプチトマトの赤が映えていた。から揚げに刺さったカラフルな串も目に楽しい。
弁当箱の半分にはおにぎりが詰められている。・・・素人目にも、相当の手間ひまをかけて作られたものだと分かった。
「えーっとね。このおにぎりが梅で、これが鮭で、これがツナだからね」
「・・・ツナ? みのりの中では邪道だったんじゃなかったか、シーチキンは?」
「うん。絶対邪道だと思うよ。・・・だけど」
「だけど?」
「・・・そ、その、溝口さん喜んでくれるかなーって思って・・・」
真っ赤になって俯くみのり。語尾は小さくて聞こえなかった。
思わずこちらまで恥ずかしくなってしまう。この年にもなって何を学生っぽいことを・・・思いつつ、こういうやりとりが楽しくて仕方が無い自分がいる。
ただの弁当箱でありながら、きっとこの箱の中には色んなドラマと感情が詰まっていたりするのだろう。
頬を緩ませる俺に対し、みのりは小さく『馬鹿』と呟く。
普段には『そういう雰囲気』が全く無い分、時々現れると途端に狼狽するといった、実に甘酸っぱい関係がここにあった。
「ほ、ほら、早く食べようよ」
慌てた様子のみのりに割り箸を渡される。目の前の料理達は食欲をそそらせるには強力すぎた。
「「いただきまーす」」
早速、から揚げを一つ口に運ぶ。冷めていながらも、十二分に肉は柔らかくてジューシー。自己採点で98点をマークした。
「どう?おいしい?」
「最高」
「・・・えへへ」
嬉しそうに笑うみのり。俺の返答を確かめるように、みのりも弁当箱に箸をつけていく。
「・・・うん、さすがは私だね。上出来上出来」
「この点に関しては俺も大絶賛だ。いっそ、巫女辞めて料理人になってもいいと思うぞ」
「あははっ。溝口さんは極端だなぁ・・・。まぁ、そういうのも楽しいかもね」
裾野を抜けて山頂に辿り着いた風が二人の間に柔らかく吹いた。さわさわと、辺りの草木の揺れる音だけが聞こえる。
360度に絶景が広がるこの場所は、弁当を食べるのに最高のロケーションだと思えた。
「はい。溝口さん、お茶だよ」
ステンレスの水筒には熱い緑茶が入っていたらしい。片手持った邪道なシーチキンおにぎりとの相性は抜群だった。
適度なおにぎりの塩加減と、緑茶の淡い苦味が心地よい。
ずずずずずずず・・・・・・。
「・・・溝口さん。音を立てずに飲もうね」
何やら一年前にも同じ事を言われた気がしていたが、目の前の卵焼きはそれを気にする暇を与えなかった。
青く高い夏の空の下、緩やかで優しい時間が流れていく。
・・・・・・・・・・・・・・・
大体、三個目のおにぎりに手を出そうとしていた時だった。
「・・・あー・・・。えーっと・・・。あ、あのね、溝口さん」
みのりは落ち着かない様子で、やたらそわそわしながら上目遣いに話す。
「ん?」
「その、あの、私、前から一度やってみたかっ・・・じゃなくて!その、あの、友達に”絶対にやれ”って命令されたことがあってね!」
顔は真っ赤だった。腕をぶんぶん振り回したりと、見ている分には楽しいが、本人にとっては大変な事態なのかもしれない。
こんな大慌てするみのりを見たのはここ最近になってからだなぁ・・・と、ほのぼのとその光景を眺める。
一人でエキサイトするみのりは、若干震えた箸先でから揚げを一つつまんだ。
「べ、別に、わ、私がしたいとかそういうんじゃなくて、えっと、その・・・。と、とにかくっ!」
突き出すように、それこそフェンシングの突きのような勢いで、目の前にから揚げがやってきた。
「・・・はい、あ〜ん・・・」
とことん真っ赤になっているみのりと、ぶっきらぼうに突き出されたから揚げ。その様に思わず吹き出してしまった。
「わ、笑うなっ!」
「・・・はー、はー・・・。いや、なかなか面白いぞ、みのり・・・」
「わ、私だって、その、えっと・・・。と、とにかく早く食べてよ!」
甘ったるいのか殺伐としているのか。何とも言いがたい雰囲気だったが、これが楽しくて仕方が無いのだから、俺も変わっているかもしれない。
パン食い競争か、あるいは釣り針のエサに食いつく魚のようなことを思いつつ、差し出されたから揚げを食べる。
「・・・お、おいしい?」
その質問は食べ始めた頃に聞かれた気がするが、これも大事なプロセスなんだろう。みのりにとっては。
普段から尻に敷かれてる分、こういう時くらいは・・・とイタズラ心が少しだけ騒ぐ。
「絶品だな。いい嫁になれるぞ」
ワンテンポ遅れて、みのりは目を真ん丸にして絶句していた。
「・・・え・・・。ええええっ!?」
いつもの冷淡な神明みのりはどこへやら。小動物のように辺りをキョロキョロ見渡したりする様は普段からは想像できないだろう。
勿論、こういった一面が楽しくて仕方が無い自分も自分だったりするのだろうけど。頬はにやけっぱなしだった。
「・・・・・・あーっ!! も、もう!こ、こんな恥ずかしいこと、平然と出来る人が理解できないよ!」
「またやってくれても嬉しいが」
「・・・うぅ・・・。溝口さん、絶対面白がってるよ・・・」
「正直言って、死ぬほど面白いぞ」
「・・・うう〜・・・」
赤くなった頬を必死に戻すかのように、みのりは深呼吸をし始める。
しばらくしたら、またいつものみのりに戻ってしまうのだろう。少々残念に感じる。
そう思うと、つい。
「・・・みのりは可愛いなぁ」
「っっっ!!!?」
必死に戻していた頬は、一気に先程よりも赤くなったのかもしれない。
涙目で、訴えるようにこちらを睨み付けるみのりを見ながら、
『馬鹿なことやってるなぁ自分』と思っては、こんな自分が好きになれそうな気がした。
山頂の暖かい昼食の時間はゆっくりと流れていた。
・・・・・・・・・・・・
「ふぅ、食った食った・・・」
「はい、お粗末様でしたー」
適度な満腹感。周囲の暖かい日差しも相まって、早速、食事の後の緩やかな眠気が訪れる。
みのりが手早く弁当箱を片付けたのをいいことに、一畳程度のレジャーシートの上で大の字で寝転んだ。
大きくないシートのため、ふくらはぎ以降はもはやシートの上に無いが、そんな小さいことは気にしないこととする。
視界全体に広がる夏の青空。遠近感が無くなって、どこまでも遠いような、手に届くくらい近いような、そんな空が目の前に広がった。
涼しい風が吹いて、服と髪と周囲の草花を少しだけ揺らした。雲がゆっくりと動いているのを眺める。
「ああ・・・。平和だ・・・」
「ちょ、ちょっと、溝口さん!寝ちゃ駄目だよ?」
「大丈夫・・・」
野鳥の囀りが遠くから聞こえる。蝉の声がどこか心地よかった。日差しは眩して暖かく、空気は澄んで涼しかった。
だから、このまま目を瞑ってしまうのは自然の流れだった。
「・・・大丈夫って言いながら寝ようとしないでよ・・・。もう・・・。溝口さんはどこでも寝れる人だなぁ・・・」
みのりの呆れ声も、包み込むような眠気に溶けていくように遠い。”やれやれ”といった溜息が聞こえた。
「・・・・・・しょうがないなぁ・・・。30分だけだよ?」
そう言って、みのりは眠る俺をかなり思いっきり引っ張り、頭をみのりの膝の上に乗っからせた。
いわゆる、膝枕というやつである。
「・・・重くないか・・・?」
「ううん」
夢うつつの自分にとって、ジーンズの粗い生地の感触すら心地よかった。布越しに伝わる体温はどこまでも気持ちを安らかにさせた。
「・・・みのりは膝枕が好きだな・・・」
「うん。膝枕してるとね、すごく温かい気持ちになれるんだよ」
「・・・そっか・・・・・・・・・・くかー・・・」
「・・・・・・おやすみ、溝口さん」
風が柔らかく流れて、緑の木々が少しだけ揺れた。空の青はどこまでも広がっていて、積乱雲はゆっくりと流れていた。
夏の明るい日差しは、幸せそうに膝の上の男を見つめる光景を、更に暖かなものへと変えていた。
この、穏やかにゆっくりと流れる平和な時間を、人は幸せと呼んでいるのかもしれない。
5.山道2 (午後2時〜午後4時)
またもや、ひたすらに徒歩。
1時間程度歩いた後、いきなり遊歩道から外れます。獣道のような道へ。
舗装はろくにされてませんが、何とか人が二人並んで歩ける程度には開けた道。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
「与作は木ぃ〜を切るぅ〜♪へいへいほー♪へいへいほー♪」
「みのり。登山中に歌う曲としては100%間違ってると思うぞ」
「いいの。音楽ってのはフィーリングだよ。その場のノリに合ってさえいればいいんだよ」
「何気なく爆弾発言だ・・・」
ゆったりとした昼食を終え、またもや山道を歩いていく。先程山頂にまで登ったことで、今は延々とした下り道が続いていた。
確か、足自体にかかる負担は下りの方が大きいという話を聞いたが、今にとってはとても楽な道以外の何者でもない。
正午を超え、眩い光線を放ち続ける太陽も西の空への滑空を開始している。周囲には濃密な森林の匂いが漂っていた。
どうやら人気の無いらしいこの登山道。すれ違った人は2人だけだった。
・・・・・・・
無駄話をしながら下ること1時間。
「っと。溝口さん、ストップ」
「ん?」
何の変哲もない、先程から延々と降りてきた山道。みのりは突然に脇の草木を手で払った。
「登山道はこのまままっすぐだけどね、私たちはこっちに行くんだよ」
払われた先を見れば、今までの道ほどではないが、若干舗装された感じの道が続いている。道幅はやたら細いが。
「こんな裏道、よく分かるな・・・」
「まぁね。ここ来るのこれで13回目だからね、しっかりと憶えてるんだよ。5歳の頃から毎年来てるんだよ?」
「・・・5歳の時に歩いたのか?今までの道を?」
「うん。・・・まぁ、ちょっとはおんぶしてもらったらしいけどね」
「・・・パワフルなお子様だ・・・」
みのりの体力が異常なのか、あるいは自分の体力が無いのか。自分の荒い息と額の汗が少々悲しげに感じた。
「さぁ、ここまで来ればあと少しだからね。溝口さん、頑張ろうね」
「おう」
巨大リュックを背負い直し、脇道へと入る。今までの登山道とは違い、道は狭く、勾配は急だった。
肩すれすれまで近づく木々。足元には踏み固められた土。野鳥の鳴き声は間近に聞こえた。
「・・・みのり。一応聞くが、この道って大丈夫なのか・・・?」
ばさばさっ。野鳥が空に向けて羽ばたく音が聞こえた。
「風合瀬家に伝わる、先祖代々の秘密の山道だよ。大丈夫大丈夫」
「つまり、それ以外の人は一切来ない道、と?」
「そうとも言うね」
みのりは笑顔だった。俺は『クマが出ませんように』と、正直真剣に祈っていた。
広大すぎる森の中に、二人の足音が響いては消えていく。
鬱蒼と茂った木々は空から降り注ぐ陽光をしっかりとガードし、周囲は少し薄暗かった。
夏とは思えないほどの涼しさを肌に感じる。何百年歳かも分からない木々の匂いを感じた。
どこか神秘的な雰囲気すら醸し出す、そんな山道を歩いていく。
みのりがまたもや素っ頓狂な鼻歌を歌い、周囲の神秘性を粉々に打ち砕いていた。
6.キャンプ準備 (午後4時〜午後7時)
綺麗な上流河川を横にしつつ(水源確保)、近くのプチ草原でキャンプをすることに。
みのりん一家が毎回使っていたポイントで、おじーちゃん辺りが自作した木のテーブルと椅子があったり。
テントは簡易式のドーム型テント。二人がぎりぎり入れるくらい。タープ(雨避け)は無し。
コンロは適当に石を積み上げたものを。薪は適当なそこらへんで集めた木々を。火種は持参した固形燃料で。
ランタンはきっちり持参。
溝口さんは山へ芝刈りに。みのりんは川で水汲みに。
夕食のメニューは未定。(2005.6/26)
・・・・・・・・・・・・・・
道を変えて30分程歩いただろうか。
洞窟のような森林のトンネルを抜けると、そこには陽光の眩しい草原が広がっていた。
周囲は山で囲まれている。ぽっかりと穴の空いたように、広大に広がる草原がそこにあった。
横薙ぎの風が吹き、僅かに伸びていた草達はゆらゆらと揺れる。
その光景はどこまでも綺麗で、違う世界に紛れ込んでしまったかのような、そんな錯覚さえ感じさせた。
「ここがキャンプする所だよ。 ・・・どう?すごいでしょ?」
くるりと回って、両手を広げながらみのりは笑顔で言う。その背中には草原の緑と空の青が映っていた。
思わず頷く俺に、みのりは満足げな笑みを浮かべる。
「ここはね、かなり昔にキャンプ場だったんだよ。経営不振だかで潰れちゃったんだけど、それをお祖父ちゃんが買い取ったんだよ」
相変わらずの端折りまくった説明が続く。確かに、小さいながらも水道っぽいものが見えた。
「だからね、毎年のこの時期だけはちゃんとトイレも水道も使えるようにしてあるから、安心して泊まれるからね」
『貸切なんて贅沢だよね』と笑顔で付け足す。半分はお祖父ちゃん自慢のような感じで説明は続いていた。
「さてと・・・。それじゃ、テント張る場所を決めないとね」
どこにしよう・・・と言いながらも足取りはまっすぐだった。歩くたびに足元の草がガサガサと音を立てる。
少し歩いていくと、川のせせらぎが聞こえてきた。
(BG:キャンプポイント)
「よしっ。やっぱりいつものポイントがベストだね」
そこは一つの巨木の下だった。丸太を縦半分にしたものを組み合わせたテーブルと椅子が用意されている。
見れば、石を積み上げて作った即席のかまどや、去年に使ったのであろう炭の残りなども確認できた。
ちょうど、自分からみて正面に巨木、その更に先には森林。背中には草原。左手に川・・・というセッティング。
確かに、ここはベストポジションなのかもしれない。
キャンプをするのは1,2度しかなかった自分。少しだけ心が躍った。
「素早く用意しないと。そろそろ日が暮れちゃうからね」
視線の先にある太陽はまだ明るい。しかしながら、時刻はもう4時を過ぎていた。
「よし、この荷物から別れられるなら俺は何でもするぞ!」
完全に自分の一部になってしまったかのような、そんなフィット感から抜け出すように大きなリュックを下ろす。
いきなり軽くなった背中の感触は、ずっと背負った者だけが感じ取れる最高の爽快感に違いないと確信した。
「それじゃ溝口さん、まずはテントから作るよ。作り方分かる?」
「さっぱりだ!」
「堂々と言うことでもないと思うけど・・・。 ・・・よいしょっと」
みのりは巨大リュックからテント用の布と骨組みらしきものを取り出した。
みのりでも抱えられる程度に小さいそれらは本当に寝床になりえるのかと正直不安に感じたが、組み立ててみれば三人は横になれるドーム型テントに変わった。
テント完成まで五分もかからなかっただろう。みのりは手馴れた手つきで簡単に作り上げてしまっていた。
「見事だみのり。俺は役に立たないということでもう寝てていいわけだな?」
「はい溝口さん。ハンマーとペグ(釘)ね。これでテントを固定させといてね」
「了解しました」
反論不能。ああ、こうして自分はみのりの尻に敷かれるのだ・・・。そう思っては少しだけ胸に切ないものを感じながら、悔しさをハンマーに込める。
プラスティック製の釘は柔らかい地面にズブズブと簡単に埋まっていった。これはあまりストレス解消には役に立たないことだけは理解する。
その間にも、みのりはテント内に緩衝用のマットを引き終え、必要な荷物をテーブルの上に並べていた。
「みのり。釘打ち終わったぞ」
「はい溝口さん。ここを抑えながら、ひたすらこのポンプに空気を入れまくってね」
やっと椅子に座れたと思ったら、今度はランタンが俺の目の前に出されてしまっていた。
何となくヨーロッパな雰囲気を彷彿させるフォルムの下に液体燃料が入っているらしく、それに圧力を加えなければいけないらしい。
三角フラスコを細くして逆にしたような金属部。空気穴を指で塞ぎながら手の力だけで圧力を加えていく。
かしゅっ、かしゅっ、と間の抜けた音がテーブル上に響く。自転車の空気入れのように、少しずつ抵抗が上がっていくのが辛かった。
最後の頃には指が折れるのじゃないかと思えるくらいの空気抵抗を感じながら、何とかその作業を終える。
「みのり。終わったんでそろそろ寝」
「あそこに小さい小屋が見えるよね?あそこの中に薪が入ってるから、一束持ってきてね」
「・・・了解しました」
足取りは少しだけ重く、薪の束はそれ以上に重かった。人生の苦労とは、きっとこの肩に食い込む薪のようなものなのではないかと、そんな人生哲学を誰かに問いかけた。
日は沈みかけ、一面の草原は若干の赤色を帯びていた。風が吹く度、草が揺れては囁くような微かな音を立てる。
積乱雲に褐色のコントラストが映える。いつも見ていたはずの茜色の空は、普段とは別物のように綺麗だった。
どこかの美術作品のような、そんな幻想的な光景が目の前に広がっている。
きっとみのりは満足そうにその光景を見ているのだろう。そう思いながら、即席の我が家へと歩みを進めていく。
・・・・・・・・・・
『固形燃料』という単語を知ってから30分後。薪にはやっと自らで燃え始めてくれた。
想像よりも長い戦いなだけあってか、成功した後の感動もひとしおだった。思わずガッツポーズ。
「うん、お疲れ様。少し休んでていいよ」
みのりの笑顔が天使の様に見えた。重量感のある椅子に腰掛け、テーブルに突っ伏す。登山と今までの準備の疲労がどっと溢れるのを感じた。
夕日は早々と沈み、辺りはすっかりと夜の帳が下りていた。
しゅごごごご・・・と、ガスランタンが唸りながらあたりに強い光を放射している。
風は相変わらず柔らかく吹いていたが、肌に当たる夜風はどこか涼しいものを帯びていた。
遠くからフクロウのような鳥の鳴き声が聞こえる。水のせせらぎは絶えることなく音を生み出していた。
目の前ではみのりがリズミカルにタマネギを刻んでいた。包丁から聞こえる音が心地よい。
「みのり、今日の献立は?」
「レバニラ炒め」
「!?」
「あははっ、冗談だよ冗談。 ・・・今度ここに来た時はそうするね」
にっこり。ランタンの暖色の光に照らされたみのりの笑顔が少しだけ怖かった。
「もう、駄目だよ?好き嫌いせずに何でも食べなきゃ大きくなれないよ?」
もう十二分に成長は完了しているわけだが、突っ込みを入れる気力が出なかった。予想以上に疲労は蓄積したらしい。
「あ、溝口さん。飯ごうをかまどにセットしてきてくれないかな?」
「おう」
疲れているのにすっくと立ち上がっては、脊髄反射のように命令に忠実な自分に何だか泣けてきた。
飯ごうを石かまどにセットする。飯ごうが石にあたってはコンコンと硬質な金属音が響いた。
ゆっくりと風が吹いて、少しだけ薪は赤い炎を燃やした。頭上の巨木の枝葉の擦れる音が微かに響く。
みのりの包丁の音が止まるだけで、静寂は辺りを包み込んでいる。
「・・・・・・静かだね」
「・・・そうだな」
空には綺麗な三日月が浮かんでいた。周囲の空気は凛とした静けさを湛え、深い暗闇は神秘的な雰囲気すら作り出していた。
会話が少しだけ止まる。この薄く広がる静寂は、二人にとって優しかった。
ぱちっ。小さな破裂音と共に散った火の粉が、満天の夜空に舞っては消えていく。
・・・・・・・・・・
(メモ : うーん。ここにワンクッション置いてもいいかも・・・。 08/14)
7.キャンプ 夜 (午後7時〜就寝)
辺りは真っ暗。空に三日月。虫の音と、川のせせらぎだけが聞こえます。
ランタンの暖色な光がいい感じに照らしてます。
そしてトーク。内容は適当に。
花火もいいかもね。
最後は就寝。テントは本当に狭いです。
勿論、アダルトな方向には持っていけないので、甘酸っぱさ全開な方向で。
みのりんから寄り添ってくる・・・くらいのことはイベントとして入れる予感。 いっそ腕枕というのも・・・。
(BG:一枚絵 キャンプ夜絵)
「・・・これまた豪勢だな・・・」
「えへへ・・・」
テーブルの上にはタンドリーチキンとニンジンのグラッセ等の温野菜、さらにはコーンスープとサラダが並んでいた。
飯ごうで炊いた米が今もなお湯気を立てていた。
ランタンの暖色な光がそれらを照らし、くっきりとした影を作り上げている。周囲はどこか幻想的だった。
「あとは・・・っと」
みのりはテントの裏手に流れる川へ向かい、そして戻ってきた。その両手には流水で冷えに冷えた缶ビールが一本ずつ。
俺が止める間もなく、みのりは勢いよくプルタブをひねる。散々山道で揺らされていたためか、空気の抜ける音と共にビールの泡は洪水のように溢れ出た。
「うわわわわっ。み、溝口さん、早くコップ!」
個人的には缶のまま飲むのが好きなんだけど・・・と思いつつも、紙コップを差し出す。相当溢れ出てしまったらしく、紙コップ一杯分のビールだけしか残らなかった。
「うう・・・。手がベトつくよ・・・」
みのりは水を溜めた蛇口つきのポリタンクの水で手を洗う。
「いつの間に用意してたんだよ、ビールなんて・・・」
「お祖父ちゃんに頼んどいたんだよ。溝口さん的にはやっぱりお酒が飲みたいかなあって」
「・・・ナイスだ、みのり。素晴らしい計らいだ」
「私も少しだけ飲むからね?」
「それは駄目だ」
「ふふふ〜。そう言うと思って、もう一本用意しているんだよ」
みのりは嬉しそうに、もう一本のビールのプルタブをひねる。
そして、今度は噴水の様にビールは溢れ出た。
「うわっ、うわわわわ!」
慌てるみのり。ランタンに照らされたこの光景はどこまでも微笑ましかった。
・・・・・・
「それじゃ、改めて・・・乾杯っ」
「乾杯〜」
喉を鳴らしながらビールを飲み干す。大自然の中、疲れた体に注がれるアルコールは格別だった。
「ぷはーっ!!」
「・・・う〜。溝口さん、こんな少しじゃ物足りないよ・・・」
おちょこ一杯分だけのビールを飲んだ、未成年の神明みのりの抗議はスルーする。
今日の朝には予想だにしなかった、大自然の中の和やかな夕食。ランタンの光が優しく周囲を包んでいた。
川のせせらぎが暗闇の先から淡く届く。虫たちが綺麗な音色を夜空に溶かしていく。
消火していない薪は時折、ぱちっ、と小さな破裂音を響かせる。
「どう?おいしい?今日のは結構自信作だよ」
素直に頷く。
口に運んだタンドリーチキンはスパイスの効いた肉汁を口の中に広げていき、ビールをさらに美味なものへと変えていった。
みのりはそんな俺を見ながら、無言で幸せそうに微笑んでいる。
ランタンの暖色で強い光がみのりの顔に強いコントラストを描いている。一年前の夜の神社の風景を少しだけ思い返した。
「溝口さんって、食べ物食べてる時は本当に生き生きしてるよね」
「みのりの料理が上手いからさ」
「・・・溝口さんは口が軽いなぁ・・・」
文句を言いながらも、その笑顔は柔らかかった。
食器の音と談笑の声が夜の草原に響いては溶けていく。
空には無数の星達がおのおのの光を届けていた。きっと、しばらく眺めれば流れ星も見えるのだろう。
静かな夜。大自然の一点。
ランタンの光も、川のせせらぎも、涼しい風も、静寂も、この時があり続ければいいと思う自分も。数千年も同じにありつづけた自然は優しくそれらを包んでいた。
・・・・・・・・・・・
>

「・・・ふふっ」
みのりは俺を見ながら薄く柔らかく笑った。ゆっくりと何かを感じ取っているような、そんな淡い笑顔だった。
食事が終わって、片づけをした後。テーブルの上には簡易ドリップ式のコーヒーがお互いに一つずつ並んでいた。
湯気と共に、コーヒーの香ばしい匂いが薄く広がっている。
俺は砂糖を3つ入れ、みのりはブラックのままでゆっくりと飲んでいた。
口の中に、コーヒー特有の苦味と渋味。そしてクドいほどの甘味が広がる。
そろそろ燃え尽きそうな薪が、ぱちっ、と音を立てて赤い火花を散らし、崩れた。
「? どうした、みのり?」
質問する俺に、みのりは柔らかい微笑のままに俺を見つめていた。
「何だか、溝口さんがここにいるのが不思議だなぁ・・・って思ったよ」
言って、また口を綻ばせる。
「ここってね、私にとっては沢山思い出が詰まった場所なんだよ。毎年の夏の記憶は、いっつもここのことばかりなんだよ」
みのりは脇で風に揺れる木々を見つめた。相変わらずの柔らかな微笑のまま、こちらを向きなおす。
「毎年ね、この頃になると家族全員やおじいちゃん達とここに来て、ここでキャンプしてたんだよ」
「きっと私はこういう所が大好きなんだと思うよ。こう・・・なんて言ったらいいのかな? 上手く言えないけど・・・落ち着くよね」
自分の頷きに、みのりは満足そうに笑う。
「私ね、実はあの街に住み始めたの高校入ってからなんだよ。それまで、こういう感じの田舎っぽい所に住んでたんだよ」
”小さい頃は野山を歩きまくってたよ”と続けるみのり。
自分の中ではあの街にいる神明みのりしか知らなかったからか、何となくイメージが沸かなかった。
「私は溝口さんのいるあの街は好きだよ。あの神社も好きだしね。・・・けどね。あそこは人が多すぎて、木々が無くて、何かこう・・・足りない気がしたんだよ」
「一昨年の夏休みにここに来て、この景色を見て。その時に私は気づいたんだよ。ああ、この感触が足りてないんだなぁ、って」
「別に、どっちが良い悪いとかそういう話じゃなくてね。ただ、私はこういう所が好きなだけなんだよ。ちゃんと6月には蛙の声が聞こえて、9月には鈴虫の鳴る季節感が好きなんだよ」
聞き続ける俺に、みのりは小さく、”話が変わっちゃったね”と呟いた。
「・・・だからね、この場所は私にとって色んな思い出が残ってる場所なんだよ。去年も一昨年もその前も、今でもしっかりと憶えているんだよ」
みのりの笑顔は淡く優しかった。
「私はね、去年の夏休みの時も家族とおじいちゃん達とここに来てね、来年もきっと同じような光景が見れると思ってたんだよ」
去年の夏。きっとその頃の自分も、来年の自分がこの場所にいるとは思っていなかっただろう。それ以上にこのような関係を・・・・・・。
「・・・不思議だよね。私と溝口さんがこうしてここで座ってるなんて、去年の私は予想も出来なかったよ」
そしてまた、小さく笑う。心から楽しそうに、幸せそうに、小さく笑った。
「・・・ごめんな、みのり」
思わず出た謝罪は、目の前のみのりではなく、去年もここにいたであろうみのりに向かって言ったのかもしれない。
「・・・お互い様だよ」
答えるみのりの表情は、どこまでも優しく淡い笑顔だった。
頭上の星空で、流れ星が輝いてはすぐさま消えた。
月は明るく、ランタンの音がうるさくて、二人を抜ける風は涼しかった。
・・・・・・・・・・・・・・
(まだみのりんキャンプ絵で)
「・・・不思議だなぁ・・・」
軽い談笑の後、みのりは再度同じ台詞を話した。
「何が?」
「何で私、溝口さんを選んじゃったのかな、って」
コーヒーを噴き出しそうになったのを寸前で堪えた。
平然と、限りなく問題のある言葉を発したみのりは、問題の重さとは正反対に軽く言い放っていた。
言うなれば、マジシャンの手品を見て『うわー、不思議だなぁ』と言っているのと同じような軽さだった。
「・・・もしかして、後悔してるのか?」
「ううん」
思い出話。
5歳上でもいいじゃない話。
人生は面白い的。
何となくイマイチなので保留。ただ、何か一つ小さく入れたいね。
>
;BG 川原
昨日も一昨日も何百年前も静かだったはずの川原に、やかましい二人の声が響いていた。
「溝口さん溝口さん!行くよー!!」
「来るなー!!!」
ぱしゅっ!!
みのりの手持ち花火『36連七色紫陽花筒』から、緑の火花を散らす何かが発射される。
言うまでも無く高温のそれは1秒前まで俺がいた所を通過し、放物線を描いきながら川へと落ち、その光を消した。
「花火を人に向けるなっ!」
「えー?溝口さん、こういうことしなかった?」
ぱしゅっ!!
そんなことを話す間も『36連七色紫陽花筒』からは容赦なく火花が発射されていく。しっかりと筒の先は俺に固定されたままに。
勢いの足りなかった青の火花は俺の手前で落ちて、ぷしゅっ、と気合のない音を出して消える。
「落ち着けみのり!それ、『絶対に人に向けないで下さい』って書いてあるだろ!!」
「困ったね溝口さん、暗くて見えないよ〜!」
ぱしゅっ!!
飛び出す赤の火花。たまたま手にしていた木の棒で、その火花を一薙ぎする。弾けた音と共に、火花は四方に拡散して空中で消えた。
「わ、溝口さんすごいね〜」
思わずサムズアップ。正直な所、さっきの瞬間はちょっとだけ楽しかった。
「ふっ、こう見えても俺は昔」
ぱしゅっ!!
今度の紫の火花は俺の服に直撃した。服には何の損傷も無かったが、冷汗はしっかりと流れた。
「みのりちゃん、1ポイント〜」
「いい加減にやめんかっ!」
ぱしゅっ! 打ち出された白色の火花をかわす。
「む〜・・・。しょうがないなぁ。それじゃ、溝口さんもこれ持って撃ち合いっこする?」
もう一本の武器を取り出して満面の笑顔を浮かべるみのりに、軽めのチョップの音が鈍く響いた。
夏の夜空に、射出された極彩色の火花が舞った。
放物線を描いて飛ぶそれは、風情があるのか無いのかよく分からない、そんな花火だった。
ただ、見上げた星空は限りなく綺麗に見えた。
・・・・・・・・・・・・
しゅごごごごごごごご・・・・・・。
噴出音を上げながら、地面に置かれた噴き出し花火から火花が噴水のように発射されていく。
眩い光が当たり一帯に広がっていた。
「綺麗だね・・・」
うっとりとその光景を見つめるみのりの言葉に強く頷く。やっぱり、花火はこうありたいものだとつくづく思う。二の腕の火傷が少しだけ痛んだ。
噴き出し花火はその火花を白色から赤色に変え、最後に青色に変えて、一分もしないうちに消えた。
辺りには、薄い煙と火薬の匂いが漂う。
「さぁって、次は・・・っと」
みのりはランタンの光を頼りに、持ってきた花火セットの袋の中を探す。
それなりに大きい袋は、あの巨大リュックの何分の一かを占めていたのだろう。
みのりはまたもや噴き出し花火を取り出し、地面に設置して楽しげに導火線に火をつけた。
3mほどの高さまで噴き出す火花は、ただひたすらに綺麗に見えた。
・・・・・・・・・・・・・・
ぱちぱちっ、ぱちぱちっ・・・。
「何で、最後は線香花火って決まってるんだろうね?」
恐らく日本人の3人に1人は呟いたであろう疑問を、みのりは同じように呟いた。
俺としては、線香花火だけは何故に屈んで行うのかも疑問だった。答えは『それが風情だから』と返ってくるだろうけど。
お互いの手には『長手牡丹』という名前の、いわゆる普通の線香花火が火花を散らしていた。
先端は褐色に輝き、その形を雫のような形に変え、小刻みに振動しては花のような火花を描いた。
二人はお互いの褐色の輝きを見つめている。落とさぬように、腕をしっかりと止めながら。
ぱちっ、ぱちっ・・・。
線香花火の奏でる破裂音はあまりにも微かで、それが逆に周囲の静寂を目立たせた。
川のせせらぎが近くから絶え間なく聞こえ、木々の擦れる音すら耳に届く。
褐色の光に照らされたみのりは、薄く笑って、
「・・・うん。やっぱり、最後は線香花火だよね」
何らかの形で自己解決した結果を話した。
しばらくの間、二人は各々の線香花火を見つめていた。
ゆっくりとした、夏の静寂がそこにあった。
「・・・夏っていいよね、溝口さん」
「・・・ん」
線香花火は少しずつその勢いを無くしていく。描く火花は花からススキに変わっていく。
みのりの線香花火から褐色の塊があっけなく、ぽとり、と落ちた。
その時に浮かべた寂しげな笑顔は、きっと何年経っても忘れないのだろうと思った。
・・・・・・・・・・・・・・
>
;(SE:シャワー音)
「♪空の雨雲〜は〜私の心〜♪」
人は何故、風呂やシャワーの際に歌いだしたくなるのだろう。そんな事を考えながら熱いシャワーを浴びて、今日の疲労を拭い去る。
シャワー室を出れば、見事なまでの夜の草原が視界に広がる。山の上には月と星が輝いていた。
心地よい体の火照りを眠気に変換しながら、ランタンで光る我が家へと戻る。
・・・・・・・・・・
待っていたのは、慌てながらもどこか恥ずかしそうな、みのりのそんな表情だった。
「あ、あのね、溝口さん・・・」
みのりは明後日の方を向き、頬をかいて、そしてまた俺の方を向いて言った。
;(音楽ストップ)
「寝袋が一つ足りないんだけど・・・どうしよっか・・・?」
そして、みのりから”寝袋に張り付いてたんだけど”と、紙切れを手渡される。
『仲睦まじき事は善き事かな』
やたら達筆なその文字を見つめ、俺の脳裏に風合瀬さんの馬鹿笑いする姿が映った。
・・・・・・・・・
『じゃあ俺は寝袋無しで寝る』という言葉は、ばっさりと否定された。
「それだけは駄目だよ。この辺りは夜になるとかなり冷えるから、寝袋なしじゃ風邪引いちゃうよ」
真剣な眼差しで俺の体調を案じるみのり。だから、頷く以外の選択肢は無かった。
実際、ここは山のど真ん中であって、体調を崩しても崩さなくても山道を歩かないとならない。
「そうは言ってもな・・・。寝袋は一つだけしかないんだろう? どっちかは入れないだろうし・・・」
「そ、それなんだけど・・・。あ、あのね、溝口さん・・・」
みのりは顔を真っ赤にしながら、しどろもどろに言う。
「えっとね、この寝袋ね、結構大きいんだよ。だから、その・・・」
上目遣いで、途切れそうな小さい声で。
「・・・その・・・。い、一緒に寝るのが、一番いい方法だと・・・思うんだけど・・・」
先程からみのりが顔を真っ赤にしていたのは、こういうことを考えていたからなんだろう。
風合瀬さんの馬鹿笑いする姿が再び浮かんだ。下山したら、頬をつねるぐらいのことはしたいと思った。
・・・決して、少しも感謝なんてしていないはずだと、そんなことを自分に確かめつつ。
・・・・・・・・
ご丁寧なことに、寝袋は男の俺が入っても結構余裕があった。
ドーム型テントの天井を見つめながら、初めての寝袋の感想として『みの虫ってこんな感じなのかなぁ』と思う。
みのりは外のランタンを消し、蛍光灯のついた手持ちライトの電源を入れた。ここまで『消灯時間』という単語がしっくりきた時もないだろう。
ライトをテントの入り口にぶら下げれば、多少薄暗い程度の光がテントの中に差し込む。
みのりはテントの中に入り、ファスナー式の入り口を閉めた。
「・・・お、おじゃましまーす・・・」
暗くて見えないが、みのりの顔は未だに真っ赤なんだろうなぁと思う。
最初はゆっくりと、最後の方はあまりの狭さにじたばたしながら、みのりは寝袋に入った。
予想はしていたが、二人が入るとさすがに狭かった。下手に抱きついてるよりも密着した状態になっている。
みのりが足を動かせば、自分の足もそれに合わせて動く。
自分の肩のあたりにあるみのりの顔。向き合った状態のため、視線が重なる。シャンプーのいい匂いがした。
やたらとみのりの体温が温かくて、脳と意識がぐらっと揺れるのを感じていた。
「や、やっぱり、ちょっと狭いね・・・」
みのりは顔を上げず、自分の胸にくっつくような状態で言う。
「い、嫌だったら言ってね。その、私は寝袋無しでも寝れるから・・・」
先程、しっかりと『寝袋無しじゃ駄目』と言っていた人物とは思えないような発言は、やたらと声が震えていた。
「・・・まぁ、全然嫌じゃないわけだが・・・」
言って、照れる。確かにこれが本心なのだが・・・やはり照れる。思わず頭をかいてしまう。
「・・・・・・私も、嫌じゃ・・・ないから・・・」
みのりは俺の服を僅かにつかみながら、顔を完全に伏せて、それでもしっかりと言い切った。
・・・心臓が大きく鼓動したような気がして、頭がぐらぐらと揺れた気がした。
「・・・・・・・・・」
「・・・・・・・・・」
お互いの間を、気まずさと緊張を多分に含んだ甘酸っぱい沈黙が流れる。
眠るために入った寝袋は、さっぱりと眠気を吹き飛ばしてしまっていた。
明日も山登り・・・ということで、きちんと寝なければいけない。・・・そうは思うが、状況はそれと逆方向にひた走っていた。
やたらと早い動悸を感じながら目を閉じる。形だけでも眠りにつこうと思った時に、今更ながらにあることに気づく。
「・・・みのり。そういえば、枕が無いんだが」
常に用意周到なみのりがこんなことを忘れる辺りに、みのりの緊張度合いが見える気がした。
「・・・あ、そ、そうだったね。えっと、タオルとかリュックとかをうまく使うしか無いんだけど・・・」
腕を伸ばして、巨大リュックを引き戻す。少々枕が高い気もしたが、神社の石段の上でも寝れる自分には十二分の枕だった。
”私も”と、もぞもぞと寝袋から出ようとするみのりを制止する。
こちらを見ながら首を小さく傾げるみのり。その頭の下に、自分の腕を差し入れた。
言うまでも無く、腕枕というやつである。
よほど驚いたのか、みのりはきょとんとした顔でこちらを見つめていた。
「・・・・・・膝枕のお返し」
「・・・・・・・・・・ま、またそうやって、私を慌てさせて楽しむつもりなんだよね・・・」
そう言いながら、みのりは差し出された腕をしっかりと掴んでいた。腕にかかる重量が心地よい。
「・・・・・・溝口さんって、時々優しいよね・・・」
「いつも優しいだろう?」
「・・・うん」
そこは否定する所だろう、と心の中で思った突っ込みは、目の前の幸せそうな笑顔によって霧散した。
何だかんだで自分も単純だと、心から思う。
「・・・溝口さん」
「ん?」
「・・・山登り、楽しかったね」
「ん」
「・・・お弁当、おいしくできてたよね」
「ん」
「・・・花火、今度は神社でもしようね」
「ん」
「・・・明日も、頑張ろうね」
「ん」
「・・・ねぇ、溝口さん」
「ん?」
「・・・もうちょっと・・・くっついてもいいかな?」
答える前に、みのりの顔は自分の胸元にくっついていた。
「・・・・・・溝口さんも、どきどきしてるよね・・・。私だけじゃないよね・・・」
そう言われると、余計に自分の鼓動が聞こえるような気がした。このまま強く抱きしめようかという欲求が頭によぎる。
「・・・・・・溝口さんはあったかいなぁ・・・」
顔をうずめるみのりの頭を軽く撫でる。シャンプーのいい匂いが微かにした。
「・・・・・・もう少し、そうしてて欲しいな・・・。すごく・・・落ち着くよ・・・」
もしかしたら、みのりからそんなことを言われたのは始めてかもしれなかった。
頭を撫でているしばらくの間、緩やかで暖かな沈黙が流れた。
みのりの寝息が聞けるまでは、そんなに時間がかからなかった。
一人、小さく息を吐く。先程から頭で鳴りっぱなしのアラートも、みのりの寝顔ですっかりと静かになっていた。
「(まぁ、いいか・・・)」
目を閉じれば、大地に体が吸いつけられるような、そんな疲労と眠気を感じる。きっと、寝付くのに時間はかからないだろう。
みのりとの関係はこのラインから出ることが無かったが、この状態を幸せに感じている自分がいる。
他人以上友達未満から、一気にここまで飛び越えてしまった自分達。
この先には時間が十二分に残っている。ゆっくりと、その間を埋めていこう。そう思った。
みのりの温かい体温を感じながら、ゆっくりと意識は夢の中へと溶けていく。
リリリ・・・。と、少々早い鈴虫の声が夏の夜に響いていた。
8.キャンプ 朝 (午前7時〜午前9時)
爽やかに。溝口さんの起床は8時。既にみのりんは7時に起き、朝ごはん製作中です。寝起きにモーニングコーヒー。
ぐでんぐでんの溝口さんと、甲斐甲斐しく料理にに勤しむみのりん。プレイヤーに『以降の二人』を連想させるように。
テントやらを片付け、再び山道へ。
・・・・・・・・・・・
山鳥の声で目覚める。こんな”爽やかな朝”を絵に描いたような目覚めは、確かに心地よいものだった。
時計を見れば午前8時。普段から比べれば、久しぶりにたっぷりと寝た気がする。
既に寝袋は自分一人で、テントの外からは心地よい包丁の音が聞こえていた。
軽く伸びをして、テントの入り口部から頭だけを出した。
「おはよー!」
朝の爽やかな日差しに、みのりの笑顔がやたら映えていた。
「♪すば〜らし〜い〜あ〜さがきた〜♪ きぼ〜の〜あ〜さ〜だ〜♪」
どこかで聞いたような歌を陽気に歌いながら、包丁はリズムよくキュウリを輪切りにしていく。
「溝口さん、寝癖すごいよ? 川で顔洗ってきたらどうかな? 冷たくて気持ちいいよ」
「おう〜」
自分でも分かるぐらいの緩慢な動きでテントを抜け出す。未だはっきりしない意識のまま、清流の流れる川へと向かった。
昨日と同じ速さで、同じ音を湛えながら流れる川。水は夏とは思えないくらい冷たく、眠気は一気に吹き飛んだ。
すっきりとした視界で辺りを見渡せば、朝のしっとりとして爽やかな空気が広がっているのを感じる。
少しだけ、みのりの上機嫌な気分が分かった気がした。
テントに戻ると、みのりがてきぱきとした動作で朝食を作っている。テーブルには湯気の立つコーヒーが置かれていた。
「みのり、何か手伝おうか?」
「ううん。溝口さんはゆっくりと座って待っててくれればいいよ」
休みたいと言うと働かされ、働こうとすると休まされる。何とも不思議な待遇だったが、お言葉に甘えることとした。
既にきちんと砂糖の入っていたコーヒーを飲む。淹れたてだったらしく、舌を少しだけ火傷した。
山鳥の鳴き声、川のせせらぎが聞こえる。朝の太陽は弱く明るい日差しを注ぎ込み、どこまでも爽やかな空気を作り出していた。
しゅうしゅう。そんな音を立てて、飯ごうから泡が溢れている。そろそろ炊き上がる頃なのかもしれない。
火を起こしている薪は、明らかに昨日の自分が作ったものよりもしっかりとした感じに見えたのが、少々悔しかった。
ぼんやりとした視線で、甲斐甲斐しく料理に励むみのりの後ろ姿を眺める。
みのりは視線に気づいては、”もうすぐ出来るからね”と笑顔で答えた。
大地に明るい日差しが差し込む。楽しげなみのりの歌声が、朝の青空に響いていく。
・・・・・・・・・・・・
テーブルには、スクランブルエッグ、ベーコン、しっかりとトマトとキュウリが鮮やかに乗ったサラダが並べられていた。
野菜をすり下ろし、調味料を簡単にブレンドして作ったドレッシングが洒落た小瓶の中に入っている。
もしかしたら、俺の担いでいた荷物の殆どは食材と調理器具だったのでは、と少しだけ思った。
「・・・相変わらず、料理は上手いな・・・」
「えへへ〜」
しっかりとバターの味わいのするスクランブルエッグと、柔らかめに焼かれたベーコンを楽しむ。
みのりはサラダを皿にたっぷりと盛り、お手製のドレッシングをかけていた。
「ところでみのり。今日は何時に起きたんだ?」
「えーと・・・。6時くらいかな?」
「色々と準備があったんだし、俺をそのまま起こしてもよかったんだが」
「・・・あんなにじたばた動いて寝袋出たのに、溝口さん全然起きなかったんだよ?起こすのは諦めたよ・・・」
・・・我ながら鈍感すぎるのではと、少しだけ思った。
「まぁ、こんな爽やかな朝を先に楽しめたわけだし、全然オーケーだよ。むしろ寝てる方が勿体無かったかもね」
みのりは少しだけくすっと笑って、さらに続けた。
「それに、誰かのために朝ごはんを作るっていうのも、結構楽しかったよ」
素直に言い切るみのりに、木漏れ日が優しく注がれていた。
朝食の時間が、ゆっくりと流れていく。
・・・・・・・・・・・・・・・
朝食を食べ終え、コーヒーで一息ついた後は、ひたすらに片づけを開始した。
しっかりと昨日の花火のゴミまで回収し、寝袋を小さく丸め、テントを畳む。
1時間としないうちに、周囲のものは巨大リュックに収納されていた。
「大丈夫。食材の分くらいは軽くなってるよ」
みのりはそう言うが、やっぱり重いものは重かった。
・・・・・・・・・・・・
一晩限りの寝床に別れを告げ、またもや山道へと歩みを進める。
みのりの話によれば、三時間程度で目的の”雪”の場所につくらしい。
楽しげに語るみのり。気づけば、自分もそれが非常に楽しみになり始めていた。
リュックを背負う力を強め、しっかりとした足取りで歩いていく。
9.山道3 (午前9時〜午前12時)
適当に。
・・・・・・・・・・・・・・・

一歩一歩歩く度に、延々と伸びている木道がくぐもった音を鳴らす。
歩いていく道は、どこまでも開けた草原の中だった。勾配もなく、ひたすらに歩き進んでいく道は非常に心地よかった。
みのり曰く、目的の場所までこのような道が延々と続くらしい。
登山というよりも散歩しているような、そんな感覚で広大な草原の中を歩いていく。
視線の先には、夏の空と、豪快に広がる積雲が見える。思わず写真に収めておきたくなるような、そんな空が広がっていた。
行きと帰り用として二本延びている木道を、二人並んで歩いていく。
「何回歩いても、やっぱりこの景色は最高だと思うよ」
みのりの笑顔に思わず頷く。
その日も、八月の空はどこまでも高く遠く青く、どこまでも広がり続けていた。
草原の中に、一陣の風が走り、草達は一つの波を作りだす。到達した風は柔らかく髪の毛を揺らした。
鳥の声は遠く、木道に響く足音は近く。
手で太陽を隠すようにして見上げた空に、二匹の鳥が悠然と羽ばたいていた。
隣を歩くみのりに視線を向ける。その先にある青空と山脈。
楽しそうなその表情は、自分のよく知っている神社での表情よりも、さらに彼女自身に近かったのかもしれない。
そんな他愛も無いことを思いながら、歩みを進めていく。
・・・・・・・・・・・・・・・
木道を歩き続けること三時間。
勾配の一切ない道は歩きやすく、休憩も無く歩きっぱなしだった。気分は実に晴れやかだったが、足は疲労を訴えていた。
長かった木道が終わり、見慣れた土の山道が広がる光景に差し掛かってすぐさま、みのりは左手の藪を手で払う。
またもや、注意しないと見つけられないような細い道が目の前に開いた。
「ここまで来たら、もう殆ど到着みたいなものだよ」
みのりは意気揚々と言うが、目の前に続く道はやたらと険しく、草はぼうぼうに生えまくっていた。
周囲は確かに涼しかったが、”雪”が降るにはとてもじゃないがまだまだ遠い気候だった。
そんな中でも、みのりは全く平然としながら、道の先を指差している。
頭の中は疑問符で一杯だったが、促されるままにその獣道を歩いていく。
地を這う木の根に躓く。やたらと足場の悪い道はたったの数分で終わり、目の前には目標地点と思しき所へと到着する。
・・・到着して、さらに訳が分からなくなっている俺を、みのりはおもしろそうに見つめていた。
10.クレーターもどき。辺りは一面のタンポポが。(午前12時〜午後1時)
締めの部分。いくら山地とはいえ、夏までタンポポが残っているかどうかは黙殺。
何やら上手い感じに風の来ない場所になっているため残っている・・・・・という方向で。
人工的に作ったっていう感じもアリ。
みのりんがどこかの石だか何だかをどかすと、一気にその中に風が。
そのままタンポポの種子が空に舞い上がって、その後に雪の様に降ってくる・・・と。
一応、ここがキモ。
・・・・・・・・・・・
「ここが入り口だよ」
「洞窟だな」
「うん。洞窟だよ」
どこまでも平然と言い切ったみのりが指差した先には、巨大な岩石が積み重なった隙間に発生した、いわゆる洞窟と言われる物が鎮座している。
洞窟なんて物とはファンタジーなゲームの中以外では出会うことなど無いと思っていたが、人生はそう上手く動かないらしい。
「・・・・・・ここに入るのか?」
入り口は容赦なく真っ暗な闇を湛え、中の様子はさっぱり見えない。それだけでも、不安を与えるには十分な要素だった。
「うん。 ・・・あ、大丈夫だよ。この洞窟、10mも無いから。ちょっと狭いかも知れないけどね。中も明るいし、全然大丈夫だよ」
みのりは臆することも無く、さっさと洞窟の中に入ってしまった。
一瞬、置いてかれた子供のような心境を感じて、感じたことに少しだけ情けなさを感じる。
「溝口さーん!早くー!」
みのりの声は閉所特有の音の反響でエコーがかかっていた。
自分も意を決し、洞窟へ入る。
がっ。
「・・・・・・」
「・・・・・・? ・・・どうしたの、溝口さん?」
「・・・荷物がつっかえて、これ以上進めない・・・」
次の大地に触れられぬままにぷらぷらと浮いている片足。そんな俺を、みのりは少しだけ呆れた顔で見つめていた。
結局、荷物は洞窟の前に置いていく事にする。全身が羽のように軽くなった気がした。
洞窟は人一人がようやく通れる程度の大きさで、天井から太陽の光が所々差し込んでいた。すべすべとした感触の岩は、冷たくてずっと触れていたい気分にすらさせた。
すぐさま出口らしき光が見える。あまりにこちらが暗いためか、出口の先は光で見えなかった。
けれども。その先に、みのりの言う”雪”があるのだろう。そんなことを確信しては心が少しだけ躍っていた。
みのりが光の中へ消え、そして自分も白に輝く出口を抜ける・・・。
・・・・・・・
;(BG:この際、背景は白一色で。全てを己の文章力に委ねて。)
サッカースタジアムのグラウンドに立ったような、そんな感覚がしたのは、あながち間違いではなかったのかもしれない。
光を抜けて広がった景色は、野球場一個分が入りそうな平坦な草原と、それを覆うようにして10m程度の壁が急な傾斜でそそり立っていた。
大地にぽっかりと空いたクレーター、あるいは火山口のような・・・。そんな地形の中に立っていた。
辺りはすっかりと壁に囲まれている。上を見上げれば、周囲の壁の形に切り抜かれた空が広がっていた。
夏の光が差し込んでいる。芝の様に短い草の広がる草原に、光の帯のように注がれている。
そして、坂と壁を足して二で割ったようなは周囲は一面に真っ白だった。綿のような何かは光に照らされ、さらにその白を際立たせていた。
それは確かに雪のように綺麗で、覆い尽くすように広がっていた。
周囲の白、空の青、大地の緑。強いコントラストを描く視界には神秘的な風景が展開している。
これが、自然の作り出した芸術と言うものなのだろう。思わず感嘆の息をもらしてしまっていた。
「・・・すごいなみのり。確かにこれは夏の雪の」
「あ、溝口さん。これは”まだ雪じゃない”からね」
俺の言葉を打ち消すように、みのりはすっぱりと言い切った。
その顔には満面の笑顔。意味ありげな台詞はまったく理解不能のものだった。
「・・・?」
「大丈夫大丈夫。すぐさま分かるからね。・・・あははっ」
みのりは楽しくて仕方が無い様子で、俺の反応を楽しんでいた。
「それじゃ溝口さん。私はちょっと”用意”してくるから、ここの真ん中で待っててね」
「・・・真ん中?」
「うん、真ん中じゃないと危険だから」
言われる言葉の一つ一つが分からなかったが、みのりに言われるままに草原の真ん中へと移動することとした。
周囲は雪のような真っ白な傾斜の壁に覆われている。”まだ雪ではない”らしい、雪のような何かは雪の様に綺麗だった。
その先には夏の空が広がっている。青と白のコントラストが綺麗だった。
草原の真ん中に到着して、ゆったりと腰を下ろす。
地面には草原。そして周囲360度を囲むようにそびえる白い壁。この光景に、野球場の真ん中で座り込んでいるような感覚を感じた。
別の世界に紛れ込んでしまったかのような感覚の中。広い空間に一人、空を見上げながらみのりの帰りを待っている。
静かに、しかしながら確実に、心のどこかがこれからの瞬間を楽しみにしていることを感じながら。
・・・・・・・・・
みのりは小走りに戻ってきたのは、この場所には風が吹いていないことに気づいた頃だった。
「溝口さん、おまたせ」
みのりの手には紐のようなものが握られていた。
それは、思わず野外用の電気のコードを連想するような長い紐で、辿っていくと遠くの壁の方まで伸びている。
色はくすんだ緑色。どこかで見たような、そんな感覚を憶える紐だった。
「さぁっ、ついにやっとお目見えだよ。・・・覚悟はいい?ちゃんと目をしっかり開けててね?」
「覚悟?」
「きっと、一生忘れない瞬間を目に出来ると思うよ」
心から楽しそうに、それこそ歌いだしそうな勢いでみのりは笑顔を浮かべる。
そして、みのりはポケットから安っぽい黄色のライターを取り出した。
ああ、確かにみのりの持っている紐は昨日の花火の時に見た”導火線”と似ているな・・・。そう思い、風景との違和感を思った。
かちっ。という音と共に、ライターは火を生み、そしてその導火線の端にその熱量を分け与えた。
みのりは素早くその導火線を地面に落とす。シューッ、と音を鳴らしながら火花は高速で壁の方へと走っていく。
「溝口さん、耳は押さえておいた方がいいかもしれないよ」
どむっ!!!!!
問いかけた言葉は、爆音に消えた。
内臓を直接揺らされているような爆音の中、その瞬間の中。みのりの先程の言葉が揺れる脳の中で反響する。
『きっと、一生忘れられない瞬間を目に出来ると思うよ』
自分は今、その瞬間の中に放り込まれたのだと、本能的に感じていた。
すべては瞬間で、何も考える暇も無くて、それでもこれから一生憶え続けるような。そんな瞬間なのだと、瞬間的に思った。
瞬きよりも短い瞬間の時間は、あくまでも瞬間であり続けながらも、伸ばされた飴のようにどこか間延びした、そんな僅かな時間だった。
爆音の瞬間。
その光景の全てが揺れた。地面が揺れ、壁が揺れ、音の振動は体を叩きつける様に響いた。
頭の中に、サー・・・、と、波の引くような、あるいはノイズのような音が反響する。
草原に、自分を中心とした円を描いた波が生まれた。それらは壁から描かれ、その円を縮めるように、音速で自分達へと向かっていく。
身構える時間も、何かに祈る時間も、みのりを案ずる時間も、瞬きする瞬間さえ、ない。
到達した爆風は互いを打ち消しあう。届いたのは僅かな微風だった。
爆風の瞬間。
壁一面を覆っていた綿のような何かが、爆風によって上空へ吹き飛んでいくのを見ていた。
小麦粉の袋を思いっきり叩いた時のような勢いで、壁から綿が放たれていく。壁は白から草の緑へと色を変えていく。
吹き荒れる爆風に吹き飛ばされていくそれらは、一つ一つがとても細かく。
そう。・・・それはまるで、雪のようで・・・・・・。
雪の瞬間。
視線は雪を追い、視界は空へと到達した。
狭まられた空に吸い込まれるようにして、雪は空へと舞い上がっていく。
空に向けて、雪が降っている。
夏の空に、雪が降っている。
爆音が通り過ぎ、爆風が消えた後。
草原の上、自分達の上に、舞い上がった雪が、雪の様に降り注いでいく。
無数の雪は陽光を所々で遮り、無数の光の筋を作り出していた。
目が眩むほどの陽光の中、夏の空の下、雪が優しく降り注いでいる。
頭の中に、蝉の声が響いていた。降り続ける雪の中で、蝉の声が響いていた。
八月の雪は、草原を白く染めるように、優しく・・・。
・・・・・・・・・・・・・
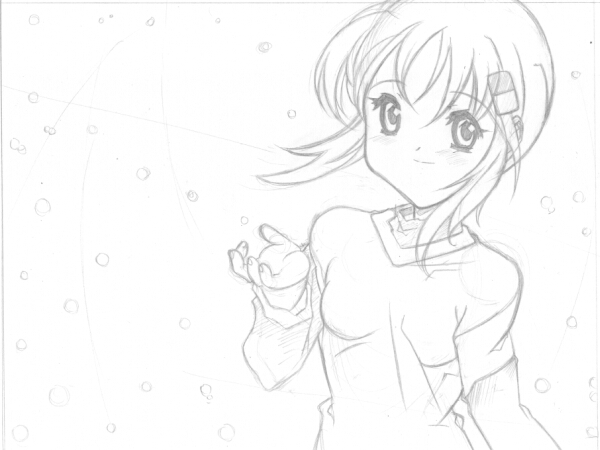
「・・・ほら、雪だよ」
夏の雪の世界の中、みのりの柔らかい言葉が響いて、時間は正常な流れを取り戻した。
みのりの周囲にも同じように、雪が降り、光の筋が注がれている。
「・・・・・・」
言葉を失っていた。広がる世界は圧倒的で、どこまでも異常で、そして綺麗だった。
「・・・綺麗だね・・・」
みのりの言葉に頷くことすら出来なかった。ただただ、光景に圧倒されていた。
どこまでも安らいでいるような、それでいて跳ね回りたい程に興奮しているような、そんな感情だけが巡っている。
雪は音も立てずに静かに降り続けている。しばらくの間、その光景を見上げ続けていた。
夏の日差しを感じながら、雪の軌道を、目で追い続けていた。
『これは今まで見てきた景色の中でも一番綺麗に違いない』なんて、曖昧なことを考えながら。
夏の空は濃い青色を広げ、降る雪を一層際立たせていた。輝くような日差しが、白に染まっていく草原を照らしていた。
「・・・来年も一緒に、ここに来ようね」
「・・・ん」
光と雪が降り注ぐ幻想的な世界の中で、みのりの柔らかな笑顔に返した俺の返事は、どこか間が抜けていた気がした。
・・・・・・・・
降り続いていた雪はやがてその量を次第に減らしていき、しばらくして止んだ。
時間にして一分も経っていなかったであろうその時間は、これから何年もの間に何回も思い出すのだと思った。
草原は白に染まっている。歩く度に、雪はふわふわと舞い上がった。
・・・・・・・・・
;BG:ブラック
「火薬を爆発させてね、タンポポの綿毛を飛ばすんだよ」
帰りの洞窟内。みのりは”雪”のメカニズムを一言で説明しきっていた。
「あの場所はね、外からの風が一切通らないんだよ。だから、タンポポの綿毛が全然飛んでなかったんだよ」
みのりはワンテンポ置いて、言葉を続けた。
「・・・あの場所はね。お祖父ちゃんがプロポーズするために、5年もかけて作った場所なんだよ。
夏まで持つようなタンポポを見つけて、周囲に風を通す管を張り巡らせたりしたんだって」
”今は毎年の夏の風物詩だけどね”と付け加えて、洞窟の出口を抜けた。
11.エピローグ的おまけ (午後1時〜)
来た道と逆の方へ歩いていくと、30分くらいでみのりんの実家付近に到着。実は近かったようです。
みのりん一家はハイキングをかねて、同じルートを辿っていたらしひ。
何で近いルートで行かないねんとツッコミ入れる溝口さんに対し、
みのりんはもじもじしながら『たまには一緒にいたかったんだもん』系の、極甘な言葉を言って、そのまま終了〜。
・・・・・・・・・・・・・
てっきり来た道を戻るのかと思っていたが、みのりが先導するままに山道の先へと歩いていく。
歩き始めて30分。リュックの重さを味わう時間も無く、視界の先には車道が横に伸びていた。
思わず口を開けてぽかんとしている俺を、車道の先で待ち構えていた風合瀬さんは面白そうに見つめていた。
・・・・・・・・・・
;SE:エンジン音 BG:道
夏空の下、山間の道路を走るライトバンの中に風合瀬さんの笑い声が響いていた。
”雪”の場所は風合瀬さん家の殆ど裏手にあり、昨日今日と俺とみのりが歩いてきた道は風合瀬家のハイキングコースだったらしい。
かなりの大回りをして、あの場所に向かったということになったが、別段何を言うつもりも無く。
むしろ楽しかったくらいなのだから、この計らいに感謝していた。
ライトバンの中には、風合瀬さんの笑い声が響いている。ハンドルが少しだけ急に回り、車体が揺れた。
助手席のみのりは顔を真っ赤にして俯き、俺は頬を掻きながら山間から覗く空を見上げていた。
昨日の夜についての質問は、風合瀬さん家に着くまでの間、機関銃の様に続いていた。
・・・・・・・・・・・
;SE:電車
がたんがたん、がたんがたん・・・。
夏の日差しの差し込む電車の中。相変わらず乗客は自分達だけだった。
車窓を流れる景色を見つめながら、肩にもたれかかって眠るみのりの体温を心地よく感じる。
空には雄大な積雲が流れている。冷房が顔に涼しい冷気を送った。
目を閉じれば、記憶の中で、雪がまた降り始めた。
じりじりと皮膚を焼くような熱気の下。青く広がる、夏空の下で。
八月の雪がしんしんと降り続く光景は、今も・・・きっとずっと、鮮明に有り続けている。
すぅすぅと幸せそうに寝息を立てるみのりの頭を優しく撫でる。
電車は大きく揺れて、みのりは『ううん・・・』と可愛らしい吐息を小さく漏らした。
その日も、夏の空はどこまでも青く、高くて、広かった。
太陽から降り注ぐ日光は熱く、強く、輝いていた。
二人を乗せた電車は高温の路面を滑るようにして走っていく。
その先には、きっと一週間前と変わらない日常と、場所が待っている。
その日も、夏の空はどこまでも青く、高くて、広かった。
太陽から降り注ぐ日光は熱く、強く、輝いていた。
雪の降る季節は、まだまだ遠い。
fin。